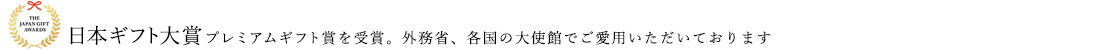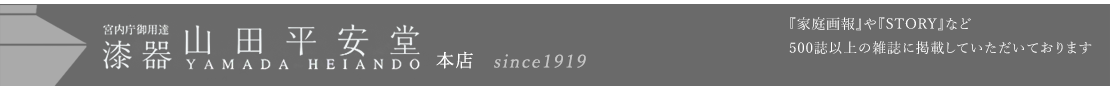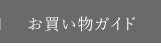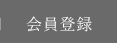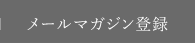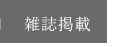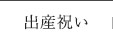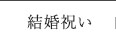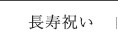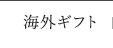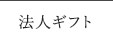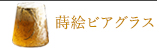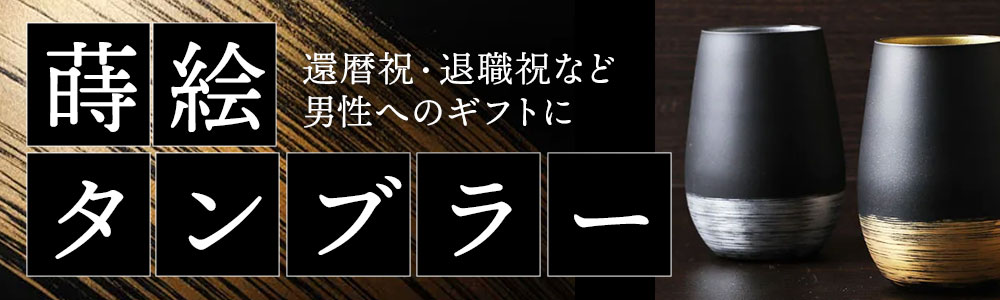旧暦の月の名前と意味を知ってる?和風月名でめぐる日本の四季

日本独自の旧暦の月の名前を指す「和風月名(わふうげつめい)」。
弥生(やよい・3月)や師走(しわす・12月)などの言葉を聞いたことがあっても、なかなか12ヶ月すべてを覚えているという方は少ないかもしれませんね。
こちらでは、そんな和風月名について、それぞれの名前を意味とともにご紹介いたします。
後半では、知ってもっと楽しい和風月名にまつわる豆知識もご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。
この記事でわかること
- ・和風月名とは?
- ・旧暦と新暦の違いは?
- ・旧暦の月の名前の意味は?
宮内庁御用達 漆器 山田平安堂

創業1919年の漆器専門店・山田平安堂。
ハレの日の器から、日常の食卓を彩る器まで、ライフスタイルに合わせて楽しめる漆器をご提案。
他にも、記念品や大切な方への贈り物など、法人様をはじめ個人的なギフトまで、国内外問わず広くご愛用いただいております。
旧暦の月の名前は「和風月名」
旧暦の月の名前は、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれています。
現代において一般的に使われている暦は「グレゴリオ暦」と呼ばれ、太陽の動きを基準にしているのに対し、旧暦は月の満ち欠けを基本とした太陽太陰暦に基づいています。
和風月名では、季節の行事や風物詩に合わせて名が付けられているため、雅な印象をお持ちの方も多いかもしれませんね。
旧暦とグレゴリオ暦では、およそ1ヶ月~1ヶ月半程度時期がずれることから、必ずしも今の季節感と合わない月もございますが、昔の人々の暮らしに思いを馳せながら意味や由来を知ると面白いのではないでしょうか。
12ヶ月の和風月名一覧
12ヶ月の和風月名を一覧でご覧いただけます。
和風月名にはいくつか名前があり、由来も諸説ありますが、そのなかでも特に有名なものをご紹介します。
| 月 | 和風月名 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1月 | 睦月 | むつき |
| 2月 | 如月 | きさらぎ |
| 3月 | 弥生 | やよい |
| 4月 | 卯月 | うづき |
| 5月 | 皐月 | さつき |
| 6月 | 水無月 | みなづき |
| 7月 | 文月 | ふづき |
| 8月 | 葉月 | はづき |
| 9月 | 長月 | ながつき |
| 10月 | 神無月 | かんなづき |
| 11月 | 霜月 | しもつき |
| 12月 | 師走 | しわす |
1月|睦月(むつき)
1月の和風月名「睦月(むつき)」は、お正月に親族や友人が集まり、宴を開いて睦まじく過ごすことからその名前が付いたとされています。
「むつびづき」や「むつましづき」「むつみづき」とも読まれます。
近年ではお正月のご挨拶に年賀状を贈る習慣が減りつつありますが、和風月名の「睦」の字にあるよう、周りの方々やご家族とのご縁にあらためて感謝をしながら過ごしてみるのも素敵です。
1月のその他の名前
・正月(しょうがつ)
・初春月/新春(はつはるづき/しんしゅん)
・太郎月(たろうづき)
・早緑月(さみどりづき)
2月|如月(きさらぎ)
2月は和風月名で「如月(きさらぎ)」。
諸説ありますが、「衣更着(きさらぎ)」とも書き、「衣類を更に重ね着するほど寒い」ころと言われております。
一方、旧暦2月頃には雪が解けて春の兆しがみられることから、梅見月や雪解月といった、春を感じられる名前で呼ばれることもあります。
2月のその他の名前
・梅見月(うめみづき)
・雪解月(ゆきげづき)
・仲春(ちゅうしゅん)
・麗月(れいげつ)
3月|弥生(やよい)
旧暦3月の和風月名は「弥生(やよい)」。
「弥」は古語で「いよいよ・ますます」という意味を持ち、弥生は「いよいよ草木が芽吹く」という意味です。
3月は現代でもひな祭りや春分の日など、春らしいイベントが盛りだくさん。
本州では例年3月下旬頃に桜が開花を迎え、名所はお花見客でにぎわいます。
3月のその他の名前
・桜月(さくらづき)
・花見月(はなみづき)
・桃月(とうげつ)
・禊月(けつげつ)
4月|卯月(うづき)
4月は、和風月名で「卯月(うづき)」。
「卯の花が咲くころ」から卯月という名前になったという説が一般的ですが、諸説あり、十二支の4番目が「卯」であることや、田植えをはじめる「植月(うづき)」に由来するとも言われています。
4月のその他の名前
・卯花月(うのはなづき)
・花残月(はなのこりづき)
・植月(うえつき)
・清和月(せいわづき)
5月|皐月(さつき)
5月は、和風月名で「皐月(さつき)」。
田植えをする季節であることから、早苗(さなえ)月が変化したと言われています。
また漢字の「皐」には、神様への捧げものである稲という意味があることからこの名になったという説もあります。
5月のその他の名前
・早苗月/早月(さなえづき/さつき)
・菖蒲月(あやめづき)
・橘月(たちばなづき)
・榴月(りゅうげつ)
6月|水無月(みなづき)
6月は、和風月名で「水無月(みなづき)」。
田んぼに水を入れる季節であることから、「水の月」と呼ばれたのが由来とされています。
漢字で「無」が充てられていることから、「水が無い月」と読まれることもありますが、「無」は「の」の当て字であるという考え方が一般的です。
6月のその他の名前
・鳴神月(なるかみづき)
・風待月(かぜまちづき)
・常夏月(とこなつづき)
・荷月(かげつ)
7月|文月(ふづき)
7月は、和風月名で「文月(ふみづき・ふづき)」。
文月という名前になった由来には諸説ありますが、旧暦7月(現在の8月)には稲が実ることから「穂含月(ほふみづき)」、また昔は七夕の夜に書物を風に当てる風習があったことから「文披月(ふみひろげづき)」と呼ばれたのが転じたとされています。
7月のその他の名前
・七夕月(たなばたづき)
・愛逢月(めであいづき)
・女郎花月(おみなえしづき)
・蘭月(らんげつ)
8月|葉月(はづき)
8月は、和風月名で「葉月(はづき)」。
葉月という名前になった由来には諸説ありますが、旧暦8月(現在の9月)には木から葉が落ちることから、「葉落ち月」が転じたものという説や、稲の穂が付く「穂張り月」から来ているという説があります。
8月のその他の名前
・秋風月(あきかぜづき)
・木染月/紅染月(こぞめづき/べにそめづき)
・月見月(つきみづき)
・桂月(けいげつ)
9月|長月(ながつき)
9月は、和風月名で「長月(ながつき)」。
夜が長くなることから「夜長月(よながつき)」、稲穂が伸びることから「穂長月(ほながつき)」と呼ばれたのが短くなり、長月となったと考えられています。
旧暦9月は、現代でいう10月~11月。
ぐっと日が短くなり寒さも堪えますが、空気の澄んだ空に美しい月を愛でることができる季節です。
9月のその他の名前
・紅葉月(もみじづき)
・菊開月(きくさきづき)
・色取月(いろとりづき)
・玄月(げんげつ)
10月|神無月(かんなづき)
10月は、和風月名で「神無月(かんなづき)」。
全国の神様たちが島根の出雲大社に集まり、不在になることからこの名が付いたと言われています。
そのため出雲地方のみでは、この時期を「神在月(かみありづき)」と呼ぶそうです。
10月のその他の名前
・神在月(かみありづき)
・雷無月(かみなしづき)
・小春月(こはるづき)
・良月(りょうげつ)
11月|霜月(しもづき)
11月は、和風月名で「霜月(しもつき)」。
旧暦11月(現在の12月頃)には、寒くなり霜が降りることからこの名が付いたと言われています。
またほかにも、雪が降るころのことから「雪待月(ゆきまちづき)」、神無月(10月)に出雲へ行っていた神様たちが帰ってくることから「神帰月(かみかえりづき)」など、様々な名前で呼ばれています。
11月のその他の名前
・神帰月(かみきづき)
・霜見月(しもみづき)
・雪待月(ゆきまちづき)
・葭月(よしづき)
12月|師走(しわす)
12月の和名「師走(しわす)」の由来は諸説ありますが、「(普段は落ち着いている)師が走り回るほど忙しい」から来ているとするのが一般的です。
この師とは僧侶のことを指し、年末年始に各地でお経をあげて駆け回る「師馳す」から来ているとされています。
大掃除や仕事納めなど、なにかと慌ただしい12月。
寒さも厳しい季節ですから、体調を崩さないよう、自愛をしながら過ごしましょう。
12月のその他の名前
・極月(ごくげつ)
・除月(じょげつ)
・春待月(はるまちづき)
・嘉平月(かへいづき)
和風月名にまつわる豆知識
ここからは、和風月名にまつわるちょっとした豆知識をご紹介します。
和風月名はいつまで使われていたの?
旧暦の月の名前である「和風月名」は、奈良・江戸時代より広く使われていましたが、明治5年(1872年)に政府によりグレゴリオ暦を使うことが決定され、翌年明治6年(1873年)以降は公文書などでは使われなくなりました。
ただし文学や暮らしの言葉の中には残り、現代でも季節感と風情のある12ヶ月の呼び名として親しまれています。
旧暦には「うるう月」がある?
旧暦は月の満ち欠けに基づいた暦であることから、太陽暦に比べてひと月が短く、そのずれを修正するために“うるう月”が設けられています。
うるう月は19年に7回の割合で挿入され、うるう月がある年は1年に13ヶ月ある年となります。
ちなみに2025年はうるう月があり、旧暦6月の次に「旧暦閏(うるう)6月」がやってきます。
【2025年のうるう月】
旧暦6月…6月25日~7月24日
旧暦閏6月…7月25日~8月22日
四季を楽しむ暮らしに。「山田平安堂」の漆器ギフト
宮内庁御用達の漆器専門店・山田平安堂では、四季折々の行事やイベントを彩る贈り物を多くご用意しております。
なにかと慌ただしい現代社会ではありますが、一日のうち、家族で食卓を囲む時間には、旬の食材を使ったお料理や季節感のあるテーブルコーディネートで、巡り行く日々の中の“ひと時”を、じっくりと味わってみませんか。
日々の食卓で楽しむ器から、季節に合わせてお部屋に飾るインテリアまで、幅広く取り揃えておりますので、この機会にぜひご覧下さいませ。
※表示価格は2025年5月20日現在のものです。